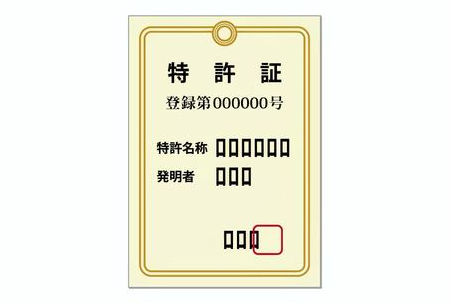
巷でよく、知的財産権という言葉を耳にしたこともあるのではないでしょうか。
実はこの知的財産権、今後海外で取引を行う場合、ここで紹介する知財戦略は欠かせないものとなるかもしれません。
輸出で保護すべき知的財産権
「知的財産権」には、主に「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」「著作権」の5つがあります。
そのうち、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
輸出に係る保護すべき知的財産権はこの4つの産業財産権です。
これらの権利は、特許庁に出願して登録されることによって、一定期間独占的に実施(使用)できる権利となります。
産業財産権は先に出願した方を優先すると言う「先願主義」となっており、先に出願した方を優先的に登録することとなっています。
しかし、日本の特許庁に出願して登録されても、それは日本国内で有効なものにしか過ぎません。
産業財産権は国ごとに保護されるため、国ごとに異なる登録制度や関連法規が存在します。
それぞれの権利を海外でも有効として権利保護するには、国際的な制度を活用して出願登録するか、もしくは各国で個別に出願登録する必要があります。
(国際的な登録については、こちらで解説します。)
下表に、4つの産業財産権の特徴をまとめました。
| 産業財産権 | 主な内容 |
| 特許権 | ・発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)に対する独占的な権利を保護する法的権利。 ・出願の日から20年間、独占的に業として実施(使用・譲渡など)可能。 ・侵害者には法的手段可能。 |
| 実用新案権 | ・考案(自然法則を利用した技術的思想の創作)に対する独占的な権利。 ・特許権ほど審査がない。また登録後3年以内であれば特許出願に変更可能。 ・出願の日から10年間のみ有効。 |
| 意匠権 | ・製品、部品などの工業用のデザインの独占使用を認める権利。 ・出願の日から25年間有効。 |
| 商標権 | ・特定の名称、ロゴやマークなどを保護する法的権利。 ・45種類からなる商品・役務区分の中からどれかを選んで登録(下表参照)。 ・有効期限は、登録の日から10年間。 |
以下、では、知的財産権のうち4つの産業財産権についてその内容とポイントを説明していきます。

★特許権
特許権を取得するためには、発明であること。
新規性(発明が公知の技術や知識として既に存在していること)、進歩性(発明が当該業界の専門家にとって、当然のものではなく、新規かつ進歩的なものであること)、産業上の適用可能性(発明が産業や事業において実用的に利用可能であること)、の3つの要件を満たす必要があり、特許庁でその審査が行われます。
特許権を取得すると、発明者はその特許権を侵害する他者に対して法的な手段を取ることができます。
特許権は、発明者に独占的な権利を与える一方で、その発明が公開されるので、当該特許権が出願登録されていない国においては、模倣されるリスクがあります。
★実用新案権
発明としての新規性や進歩性が、特許権ほどには求められてなく、(自然法則を利用した技術的思想の創作)に対する独占的な権利です
特許の「発明」に対して、「考案」に対する権利であり、発明と呼ぶには、革新的・技術的な発展があるわけではない創作を保護する権利といえます。
実用新案権の保護対象は、「物品の形状、構造または組み合わせに係るもの」に限られており、特許権のような「方法の考案、物の製造方法の考案」は実用新案権として登録されません。
実用新案権の登録出願においては、実体的な内容が審査される事はなく、登録申請の書類等に不備がなければ、半年ほどで設定登録されます。
特許権を取得する上での最大の難関は、3要件をクリアするための審査ですが、実用新案権ではこの審査がないと言う事は大きなメリットです。
一方、デメリットとしては、実体審査されることなく登録されるので、実際にどの範囲までが有効な権利なのかが曖昧です。
また、差し止めや賠償請求までの手間や手順が多くなっているなど、特許権と比べて必ずしも十分な保護を受けられるわけではないともいえます。
★意匠権
製品、部品等の工業上のデザインの独占使用を認める権利です。
そのため、自社製品のデザインを衣装登録しておく事は、コピー商品、類似商品などの模倣品対策に絶大な効果を発揮します。
似たような権利に「著作権」がありますが、著作権は文化面での権利であり、製品などの実用品のデザインについては著作権が認められないことが多いです。
★商標権
自社の取り扱う商品・サービスを他者のものと区別するために使用するための、特定の名称、ロゴ、スローガン、デザインなどの商標(マーク・識別標識)を保護する法的な権利です。
商標を独占的に使用することができる権利で、その効力は同じ商品や商標・サービスだけでなく、類似する範囲にも及びます。
商標権の登録には、識別力があること、不登録理由(他人の周知、先願商標と同一・類似、他人の肖像・氏名・著名な略称などを含む公の秩序、または善良の風俗を害する恐れ等)に該当しないこと、の要件を満たす必要があります。
商標権の存続期間は更新が可能であり、更新回数に制限はありません。10年ごとに更新することによって、半永久的に商標権を持ち続けることができます。

なお、ロゴの右上に®️(マルR/Rマーク)がついているのを見たことがあると思いますが、この®️は商標が登録されていることを示すものです。
®️以外にも「TM」がついている場合もあります。
TMは「Trade Mark」(商標)の頭文字を取ったもので、商標登録されているかどうかにかかわらず、商標であることを示したい場合に使います。
®️を商標と一緒に使う場合には、それが商標登録されている必要があります。
★商品・役務登録のための45区分の一覧
| 区分 | 商品分野(第1類~第34類) |
| 第1類 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 |
| 第2類 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 |
| 第3類 | 洗浄剤及び化粧品 |
| 第4類 | 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 |
| 第5類 | 薬剤 |
| 第6類 | 卑金属及びその製品 |
| 第7類 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 |
| 第8類 | 手動工具 |
| 第9類 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 |
| 第10類 | 医療用機械器具及び医療用品 |
| 第11類 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 |
| 第12類 | 乗物その他移動用の装置 |
| 第13類 | 火器及び火工品 |
| 第14類 | 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 |
| 第15類 | 楽器 |
| 第16類 | 紙、紙製品及び事務用品 |
| 第17類 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック |
| 第18類 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 |
| 第19類 | 金属製でない建築材料 |
| 第20類 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの |
| 第21類 | 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 |
| 第22類 | ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 |
| 第23類 | 織物用の糸 |
| 第24類 | 織物及び家庭用の織物製カバー |
| 第25類 | 被服及び履物 |
| 第26類 | 裁縫用品 |
| 第27類 | 床敷物及び織物製でない壁掛け |
| 第28類 | がん具、遊戯用具及び運動用具 |
| 第29類 | 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 |
| 第30類 | 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 |
| 第31類 | 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 |
| 第32類 | アルコールを含有しない飲料及びビール |
| 第33類 | ビールを除くアルコール飲料 |
| 第34類 | たばこ、喫煙用具及びマッチ |
| 区分 | 役務分野(第35類~第45類) |
| 第35類 | 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
| 第36類 | 金融、保険及び不動産の取引 |
| 第37類 | 建設、設置工事及び修理 |
| 第38類 | 電気通信 |
| 第39類 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 |
| 第40類 | 物品の加工その他の処理 |
| 第41類 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 |
| 第42類 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 |
| 第43類 | 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 |
| 第44類 | 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 |
| 第45類 | 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 |
参考:「特許庁」商品及び役務の区分解説〔国際分類第12-2024版対応〕
“知的財産権の種類” への1件のフィードバック
現在コメントは受け付けていません。