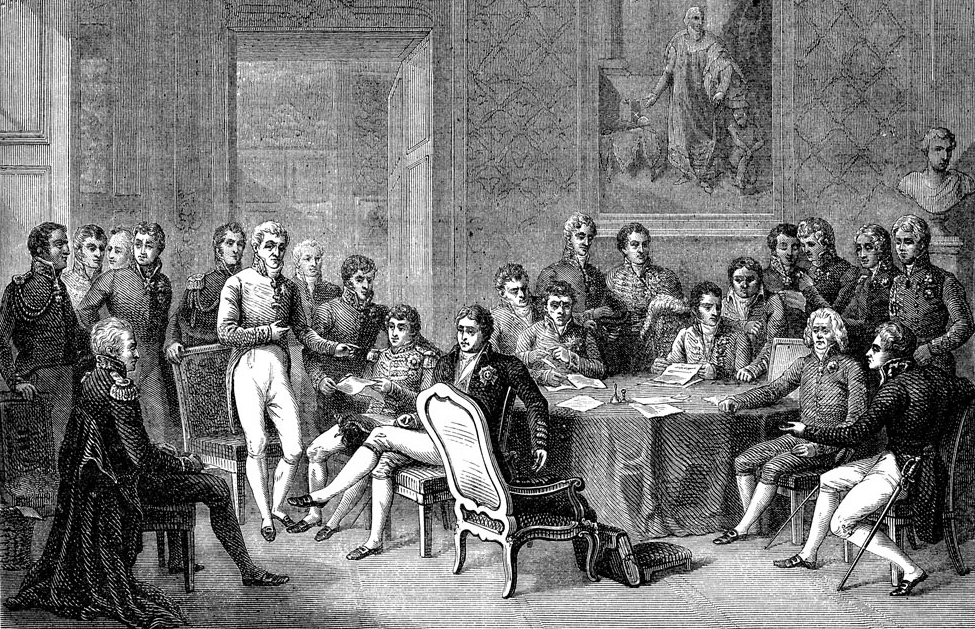
ウィーン売買条約とは
貿易取引に関わる国際条約として、インコタームズの他に1988年1月に発行した国際物品売買契約に関する国際連合条約(United Nations Convention on Contracts for the international Sale of Goods : CISG)、通称、ウィーン売買条約(Vienna Sales Convention)があります。
この条約は、国際的な物品の売買契約について、その成立及び契約当事者の権利義務に関する事項を101条にわたって規定しており、取引にいずれの国の法が適用されるかという不確実性が解消され、安定した円滑な取引が可能となります。
同条約の適用範囲は、取引当事者の国籍や法人設立地に関係なく、異なる締結国に所在する企業間の契約となり、消費者の取引には原則として適用されません。
この条約は任意規定であり、当事者の合意を優先するので、条約の適用を排除したい場合には、契約において一部又は全部の適用を排除することを定めることも可能ですし、当事者間で特約があればそれが優先します。
加盟国は2024年時点で97カ国、署名済みだが、未批准が18カ国となっています。
締約国はこちらのサイトで確認することが可能です。
締約国は増えており、今後、加盟国の増加に伴って、ウィーン売買条約が適用されるケースが増加するものとも考えられています。
最新の締約国は、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL:アンシトラル)ウェブサイトでも確認することができます。
日本は2009年8月1日に国会で加入が承認され、同日付で発効、71番目の加盟国となりました。
インコタームズとの違いは?
インコタームズの方が歴史も古く、一般的に広く利用され、航空輸送の発展や海上コンテナ輸送など、輸送手段の近代化や輸出入業者など貿易当事者のニーズに対応して10年ごとに改訂されてきました。
それでも、国際的な物品売買に関する統一法を制定することによって、法的な裏付けを確立し、貿易取引の健全な発展を促進するために、1980年4月にウィーンで開かれた外交官会議で、この条約が採択され、1988年1月1日に発効されています。
既に国際物品売買の準拠法として、世界標準ルールとなっています。
インコタームズとウィーン売買条約の違い
〇:規定あり ×:規定なし
| インコタームズ | ウィーン売買条約 | |
| 売り手と買い手の義務 | 〇 | 〇 |
| 危険移転の時期 | 〇 | 〇 |
| 契約の成立 | × | 〇 |
| 契約違反に対する救済 | × | 〇 |
| 契約の有効性 | × | × |
| 所有権の移転時期 | × | × |
インコタームズとウィーン売買条約どちらが優先?
インコタームズとの関係では、インコタームズに同様の規定があれば、インコタームズが優先します。
インコタームズ、ウィーン売買条約ともに、「売り手と買い手の義務」及び「危険移転の時期」の規定がありますが、この場合これらの規定はインコタームが優先します。
インコタームズに規定されていない範囲で、ウィーン売買条約が適用されます。
ウィーン売買条約の主な内容は次の通りです。
「契約の成立」:
契約成立は、承諾の到達時と規定しています。
申し込みと承諾の完全一致の原則を緩和し、申し込み等承諾の内容が多少異なっても些細な相違であれば契約の成立を認めています。
「当事者の権利と義務」:
契約の解除は、重大な契約違反の場合に限ると制限しています。
また、契約違反に対する救済手段についても、相手方が契約に違反することが予想される場合には、期限前の契約解除など予防的な方法も規定しています。
インコタームズもウィーン売買条約も、国際取引にとってはとても重要な「契約の有効性」や「所有権の移転」については規定がありません。
これは国によって関係法が異なっていることなどが大きな要因となっています。